耳鼻いんこう科・頭頸部外科
ごあいさつ
特色
当科の特徴は、臨床経験の豊かなスタッフを多数擁し、重症を含む幅広い疾患に迅速に対応できることです。2023年7月現在、常勤では、耳鼻咽喉科頭頸部外科医師12名が在籍しております。そのうち、耳鼻咽喉科専門医が8名、頭頸部外科専門医が5名を数えます。2022年の1年間に行った延べ手術症例数は、耳鼻咽喉科頭頸部外科全体で712件でした。内訳として頭頸部悪性腫瘍手術は再建手術となった32件を含めて201件を行いました。総合病院の強みを活かして、他院での対応が難しい循環器合併症のある頭頸部悪性腫瘍症例の治療等も積極的に行っております。悪性腫瘍手術以外にも、耳科手術、鼻科手術、感染症を含めた耳鼻咽喉科の幅広い疾患に標準治療を行っております。ほかにも経験豊富なスタッフの存在を背景に、主に県北から集まる緊急手術症例の受け入れにも対応しております。
診療内容
耳科疾患
急性扁桃炎、めまい、突発性難聴、メニエール病、慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎、耳硬化症、耳管機能障害、顔面神経麻痺など
突発性難聴やメニエール病をはじめとする急性感音難聴に対しては難聴の程度に応じて外来または入院にてステロイド剤や抗凝固剤、利尿剤などを用いた治療を行っています。
めまいで緊急受診される患者さんに対しては外来にて中枢疾患との鑑別を行ない、必要があれば、入院の上検査や治療をします。
慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎などに対しては年間約70例の手術を施行しており、高度難聴に対する人工内耳埋め込み術にも対応しております。
補聴器装用のための検査やスタッフも充実しており、年間約100例の補聴器相談新規患者さんの診察にあたっています。
顔面神経麻痺に対してはステロイド剤・抗ウィルス剤・循環改善剤などによる点滴治療を行い、適応があれば手術療法(顔面神経減荷術)も行っています。
鼻科疾患
アレルギー性鼻炎、鼻中隔弯曲症、副鼻腔炎、鼻茸(ポリープ)、鼻出血など
鼻づまりや鼻水の原因として、アレルギー性鼻炎、肥厚性鼻炎、慢性副鼻腔炎、鼻中隔弯曲症などの病気があります。
慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下副鼻腔手術(ナビゲーション下)、鼻中隔弯曲症や肥厚性鼻炎に対する鼻中隔矯正術、下甲介切除術を行っています。アレルギー性鼻炎に対する鼻茸(ポリープ)切除術は日帰りまたは1泊2日で行っています。
また、アレルギー性鼻炎に対しては投薬などの対症療法だけでなく、特異的減感作療法も行っています。
口腔・咽頭疾患
扁桃炎、アデノイド、睡眠時無呼吸症候群など
扁桃摘出術の適応は扁桃炎を1年に3~5回以上繰り返している場合、IgA腎症や掌蹠膿胞症の診断を受けて手術を勧められた場合、口蓋扁桃や咽頭扁桃が中耳炎や咽頭閉塞の原因となっている場合などです。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸では、寝ている時に空気の通り道(上気道)が狭くなり呼吸がしにくくります。症状には、いびき、日中の眠気、起床時の頭痛、疲れやすさなどがあり、重篤な場合には、突然死などの危険もあります。睡眠中に検査を行なう必要があり、スクリーニング検査のために簡易モニターの貸し出しを行なっております。診断確定のための精密検査として、1泊2日の入院をしていただき、脳波や心電図、呼吸の状態を調べるポリソムノグラフィーを実施しております。外科的治療としては、鼻中隔矯正術や口蓋形成術、口蓋扁桃摘出術などの手術を行い、保存的治療としてはマスクによる夜間の呼吸補助装置(鼻マスク式持続陽圧呼吸:CPAP)やマウスピースの装着などを循環器内科や口腔外科と連携して行っています。
喉頭疾患
声帯ポリープ 、ポリープ様声帯、声帯結節、喉頭肉芽腫、喉頭乳頭腫、発声障害など
声帯の炎症・ポリープ・腫瘍は声がれ、誤嚥、呼吸困難の原因となることがあります。これらに対しては、禁煙指導、内服治療、吸入、リハビリ、手術などを行う必要があります。
頭頚部疾患
舌、歯肉、口腔底、頬粘膜、喉頭、上・中・下咽頭、鼻腔、副鼻腔、耳下腺、顎下腺、甲状腺、頸部食道、気管、聴器などの良性及び悪性腫瘍 嚥下障害など
良性腫瘍:
耳下腺、顎下腺、甲状腺、傍咽頭間隙などの手術施行しております。
悪性腫瘍:
放射線科、化学療法室と連携し、口腔癌、喉頭癌、咽頭癌、頸部食道癌、鼻・副鼻腔癌、甲状腺癌、唾液腺癌などの治療を行っております。NBI(特殊光)内視鏡を用いて口腔や咽喉頭の早期癌の発見に努めており、早期癌では内視鏡下手術による低侵襲な治療を行っております。進行癌では形成外科、口腔外科、脳外科、外科と連携して可能な限り機能温存に努めております。
術後は当科専属の言語聴覚士によるきめ細かなリハビリテーションを行っております。
心・腎疾患などの合併症のある患者さんの手術にも、他科と連携して積極的に取り組んでおります。
診療実績
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 新規入院のべ患者数 | 965件 |
| 紹介患者数 | 1,848件 |
| 手術件数 | |
| 耳科領域 | 74件 |
| 鼻科領域 | 187件 |
| 口腔・上中咽頭領域 | 178件 |
| 喉頭・気管・下咽頭・食道領域 | 137件 |
| 顔面・頸部領域 | 186件 |
| 悪性腫瘍手術症例 | 177件 |
※2021年度実績
教育・研修・研究
専攻医(後期臨床研修医)への積極的な指導
症例数は多く、疾患概念を理解した上で基本的な診療技術の習得から手術手技まで積極的な指導を行っています。
専門医認定プログラム
耳鼻科の常勤医師は全員耳鼻咽喉科専門医を取得しております。当科は日本耳鼻咽喉科学会研修指定病院です。
院長

徳永 英吉
とくなが えいきち
詳細は院長のページへ
科長(耳鼻いんこう科)

大﨑 政海
おおさき まさみ
医学博士
日本耳鼻咽喉科学会 代議員
日本耳鼻咽喉科学会埼玉県地方部会 常任理事・代議員
日本頭頸部外科学会 評議員
日本頭頸部癌学会 代議員
取得資格
- 日本耳鼻咽喉科学会/日本専門医機構 耳鼻咽喉科専門医・専門研修指導医
- 日本頭頸部外科学会 頭頸部がん専門医・指導医
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 耳鼻咽喉科専門研修指導医
- 日本形成外科学会/日本専門医機構 形成外科専門医
- 日本形成外科学会 自家脂肪注入術特別セミナー受講
- 厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了
- 厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了
科長(頭頸部外科)

畑中 章生
はたなか あきお
取得資格
- 日本耳鼻咽喉科学会/日本専門医機構 耳鼻咽喉科専門医・専門研修指導医
- 日本耳鼻咽喉科学会/日本専門医機構 補聴器相談医
- 日本頭頸部外科学会 頭頸部がん専門医
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 耳鼻咽喉科専門研修指導医
- 厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了
- 厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了
副科長(耳鼻いんこう科)

原 睦子
はら むつこ
取得資格
- 日本耳鼻咽喉科学会/日本専門医機構 耳鼻咽喉科専門医・専門研修指導医
- 日本耳鼻咽喉科学会/日本専門医機構 騒音性難聴担当医・補聴器相談医
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 補聴器相談医
- 日本嚥下医学会 認定嚥下相談医
- 厚生労働省 補聴器適合判定医師研修会修了
- 厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

三ツ村 一浩
みつむら かずひろ
取得資格
- 日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医・専門研修指導医
- 日本頭頸部外科学会 頭頸部がん専門医
- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
- 日本口腔・咽頭科学会 植込み実施医「所定の研修」修了
- 厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了
- 厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了

木下 慎吾
きのした しんご
取得資格
- 日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医・専門研修指導医
- 日本耳鼻咽喉科学会 補聴器相談医
- 日本頭頸部外科学会 頭頸部がん専門医・指導医
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 補聴器相談医
- 日本耳科学会 耳科手術指導医
- 厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了
- 厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了
副科長(頭頸部外科)
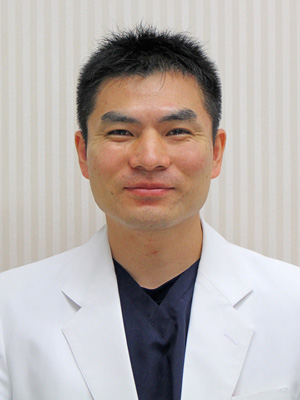
久場 潔実
くば きよみ
取得資格
- 日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
- 日本頭頸部外科学会 頭頸部がん専門医・頭頸部がん専門医制度指導医
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 耳鼻咽喉科専門研修指導医
- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
- 厚生労働省 がん診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了
- 厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了
医員(耳鼻いんこう科)
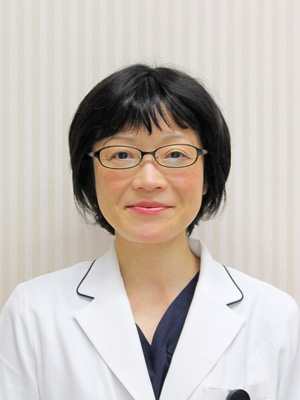
間中 和恵
まなか かずえ
取得資格
- 日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医・専門研修指導医
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 補聴器相談医
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 嚥下障害講習会修了
- 厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

長野 恵太郎
ながの けいたろう
取得資格
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会/日本専門医機構 耳鼻咽喉科専門医
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 嚥下障害講習会修了
- 厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

迎 亮平
むかえ りょうへい
外来担当医表
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 | 徳永*大﨑*畑中間中担当医① | 原三ツ村久場長野 | 間中担当医① | 原担当医① 【頭頸部外科】 西嶌* |
徳永*大﨑*間中木下迎 | 徳永 (第2週のみ)*担当医①担当医②第1・3・4・5週 担当医③ |
| 午後診 | 徳永*迎三ツ村 | 担当医①担当医② | 担当医① | 担当医①担当医②第1・3週 睡眠呼吸外来* | 大﨑(IC)*木下担当医①第1・3週 畑中(IC)* |
女性医師は赤字で表示しています
*がついている医師は予約が必要です。
予約外の受付時間は火・水・木のみ午前11:00までです。
時間帯予約制のため、予約外の方は待ち時間が長くなることが予想されます。ご了承ください
担当医と表示してある欄には当日に医師が決まります。
診療時間が変更になる場合がございますので、 詳しくは外来へお問い合わせください。
| 外来受付時間 | 平日 午前8:00~12:00、午後12:05~16:30(土曜日は、午前のみ) |
|---|---|
| 診察開始時間 | 平日 午前9:00~、午後14:00~(土曜日は、午前のみ) |
| 休診日 | 日曜日、祝日、年末年始 |
休診・代診のお知らせ
| 診療変更日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/26(金) | 午前 | 大﨑 | なし |
| 2025/12/29(月) | 終日 | 大﨑 | なし |
| 2026/01/05(月) | 終日 | 大﨑 | なし |
| 2026/01/23(金) | 午前 | 大﨑 | なし |
| 2026/01/24(土) | 終日 | 担当医③ | なし |
| 2026/01/27(火) | 終日 | 担当医① | なし |
| 2026/02/02(月) | 終日 | 大﨑 | なし |
| 2026/02/06(金) | 終日 | 木下 | なし |
| 2026/02/20(金) | 午前 | 大﨑 | なし |
| 2026/03/02(月) | 終日 | 大﨑 | なし |
| 2026/03/23(月) | 終日 | 大﨑 | なし |
| 2026/04/03(金) | 終日 | 大﨑 | なし |
予約受付窓口
紹介状をお持ちの方
地域連携課・病診連携係
紹介状をお持ちでない方
外来予約センター
受付時間
| 平日 | 8:00~12:00、12:05~16:30 |
|---|---|
| 土曜 | 8:00~12:00 |
- 紹介状を開封せずにお手元にご用意ください。
- 当日のご予約はお受けいたしかねます。
- 当院は地域医療支援病院です。原則として、かかりつけの医院からの紹介状が必要となります。
