病理診断科について
ごあいさつ
特色
医療の質の向上に病理診断が貢献しています。
症状・診察や血液・X線検査だけでなく、必要な場合、患者さんの体の一部から組織が採取され、病理医がミクロレベルで診断を下します。臨床診断が組織学上も合致するか否か、病理は医療の質を向上させる役割を担っています。特に癌の診断には必須です。
症例は多数、複数の病理専門医が二重チェックを実施します。
当院の年間検体数は組織診で約9,500、細胞診で約17,000、有数の症例数です。5名の病理専門医が全症例に二重チェックを実施し、更に、稀少・難解例はその領域を専門とする第三者に意見をお願いし、正確な診断の為に幾重ものシステムを構築しています。
個々の患者さんの病理診断の確認・未確認を追跡調査しています。
病理診断科では病理診断報告書を臨床担当医が確認済みか否か、電子カルテ上で調査し、未確認症例は担当科に伝えます。医療安全の仕組みを遂行しています。
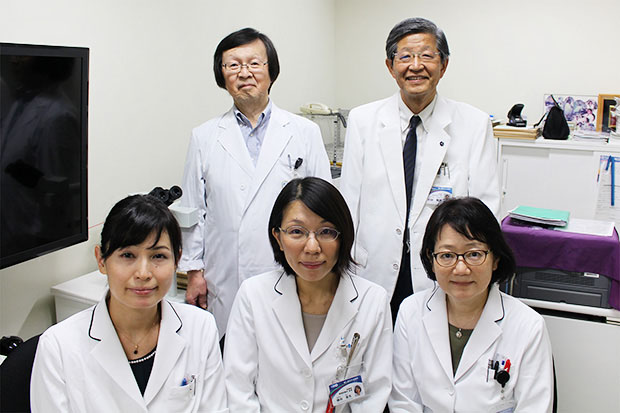
教育・研修・研究
教育・研修
初期臨床研修・専攻医研修(後期臨床研修)プログラムを準備し、研修医の病理研修を引き受けています。臨床に即した病理診断の基本的事項の教育、および各研修医の希望に合わせた各臨床科の特徴的な症例を中心に研修指導を行っています。
学会報告・研究
当科における組織診・細胞診をもとにして、症例検討会や学会等での症例報告、および医学雑誌への投稿を行っています。臨床医の症例報告の場合は判りやすく鮮明な画像を提供し、研究では学術的なサポートをしています。
科長

杉谷 雅彦
すぎたに まさひこ
主な経歴
- 長崎大学医学部卒業
- 長崎大学医学部第二内科 医局員
- 日本大学大学院医学研究科博士課程(病理系病理I専攻)終了
- 日本大学医学部病理学講座(分野) 助手・講師・助(准)教授
- The Lindsley F. Kimball Research Institute of the New York Blood Center, Laboratory of Virology 客員研究員
- 日本大学医学部形態機能病理学分野 教授(主任)
- 日本大学医学部附属板橋病院 病理部長(兼任)
- 日本大学医学部総合医学研究所 所長(兼任)
- 上尾中央総合病院 病理診断科 科長、現在に至る
- 日本大学医学部客員教授(兼任)
取得資格
- 日本病理学会/日本専門医機構 病理専門医・病理専門医研修指導医
- 日本臨床細胞学会 細胞診専門医・教育研修指導医
- 厚生労働省 死体解剖資格認定医
- 厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了
診療顧問
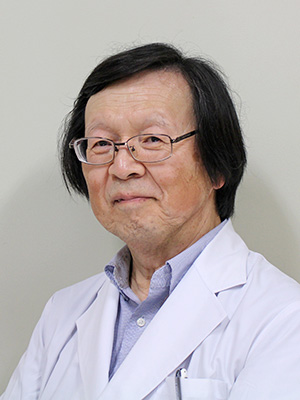
長田 宏巳
おさだ ひろみ
取得資格
- 日本病理学会/日本専門医機構 病理専門医・病理専門医研修指導医
- 厚生労働省 死体解剖資格認定医
- 厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了
副科長

絹川 典子
きぬかわ のりこ
取得資格
- 日本病理学会/日本専門医機構 病理専門医・病理専門医研修指導医
- 日本臨床細胞学会 細胞診専門医・教育研修指導医
- 厚生労働省 死体解剖資格認定医
- 厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了
医長
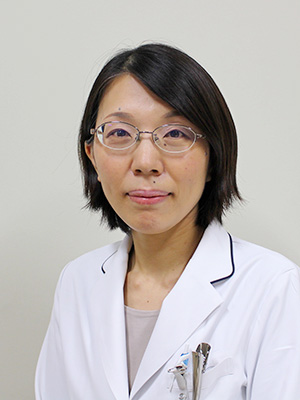
横田 亜矢
よこた あや
取得資格
- 日本病理学会/日本専門医機構 病理専門医・病理専門医研修指導医
- 日本臨床細胞学会 細胞診専門医
- 厚生労働省 死体解剖資格認定医
医員

大庭 華子
おおば はなこ
取得資格
- 日本病理学会/日本専門医機構 病理専門医
- 日本臨床細胞学会 細胞診専門医
- 厚生労働省 死体解剖資格認定医
守川 春花
もりかわ はるか
予約受付窓口
紹介状をお持ちの方
地域連携課・病診連携係
紹介状をお持ちでない方
外来予約センター
受付時間
| 平日 | 8:30~17:30 |
|---|---|
| 土曜 | 8:30~13:00 |
- 紹介状を開封せずにお手元にご用意ください。
- 当日のご予約はお受けいたしかねます。
- 当院は地域医療支援病院です。原則として、かかりつけの医院からの紹介状が必要となります。
